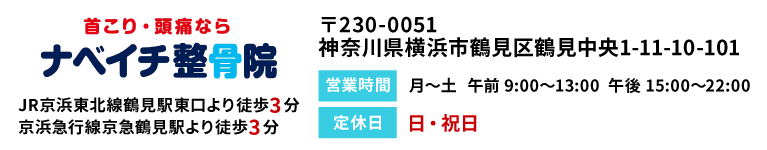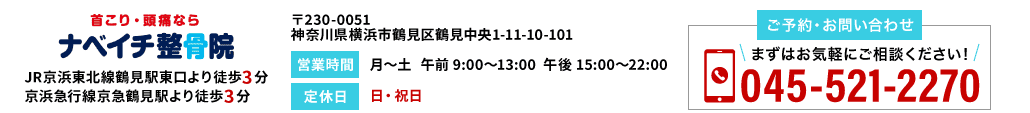こんにちは。
わたなべです。
今日は私たちを悩ませる「痛み」について解説していきます。
特に2017年に国際疼痛学会であらたに定義された第三の痛み「痛覚変調性疼痛」を中心に書いていきます。
「痛み」は3種類ある? 〜痛覚変調性疼痛とは何か〜
私たちが感じる痛みには、大きく分けて 3つの種類 があります。
- 侵害受容性疼痛(しんがいじゅようせいとうつう)
→ ケガや炎症による痛み。例:「転んで膝をすりむいた」「ぎっくり腰になった」 - 神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)
→ 神経が傷つくことで生じる痛み。例:「ヘルニアによる神経痛」「帯状疱疹後の痛み」 - 痛覚変調性疼痛(つうかくへんちょうせいとうつう)
→ 脳や神経が誤作動を起こし、痛みが続く状態。例:「ケガが治ったのに痛みが続く」「検査では異常なしなのに体が痛い」
この 「第三の痛み」 である 痛覚変調性疼痛 は、従来の痛みの概念とは異なり、「脳の誤作動」によって痛みが生じることが分かってきています。
では、具体的にどのようなメカニズムで起こるのか? どうすれば改善できるのか?
詳しく見ていきます。
痛みが続くのはなぜ?「痛覚変調性疼痛」という新たな視点

「もうケガは治ったはずなのに、なぜかずっと痛い……」
「検査では異常なし。でも、体が痛い……」
こうした症状に悩んでいる人は少なくありません。
それは 「痛覚変調性疼痛(つうかくへんちょうせいとうつう)」 かもしれません。
最近の研究では、「痛み」は必ずしも体の損傷や炎症だけが原因ではなく、脳や神経の働きが変化することで、痛みが過剰になったり長引いたりする ことが分かってきました。
では、痛覚変調性疼痛とはどのようなものなのか? どうすれば改善できるのか?
今回は、最新の知見を交えながら、できるだけ分かりやすくお伝えします。
痛覚変調性疼痛とは?
通常、私たちの体は 「危険があるときに痛みを感じる」 ようにできています。
例えば、指を切ったときや足をくじいたとき、痛みがあるからこそ「これは危ない!」と気づき、体を守る行動をとります。
しかし、痛覚変調性疼痛の場合は違います。
体のケガや炎症が治っていても、脳や神経が誤作動を起こし、痛みを感じ続ける のです。
たとえばこんなイメージです。
火災報知器の誤作動
火事が起こったときに鳴る「火災報知器」をイメージしてみてください。
本来は 「火があるときにだけ鳴る」 ものですが、火が消えた後もずっと鳴り続けたらどうでしょう?
本当はもう火がないのに、「危ないぞ!」と警報が鳴り続けてしまう。
これと同じことが、痛覚変調性疼痛では起こっているのです。
どんな人がなりやすい?
痛覚変調性疼痛は、特定の状況で発生しやすいことが分かっています。
① けがや病気の後、痛みが続くケース
・骨折や捻挫が治ったのに、痛みだけが残る
・ぎっくり腰を起こしてから、慢性的に腰が痛い
・帯状疱疹(たいじょうほうしん)後の神経痛が長引く
このように、本来は治るはずの痛みが続くのが特徴です。
② ストレスが多い人
ストレスは、脳の痛みを感じるシステムを過敏にします。
・仕事のプレッシャーが大きい
・人間関係の悩みがある
・睡眠不足が続いている
こうしたストレスがあると、脳が「痛みを強く感じるモード」に入ってしまう ことがあります。
③ 運動不足の人
長時間のデスクワークや、座りっぱなしの生活が続くと、筋肉がこわばり、痛みを感じやすくなります。
・「ずっと同じ姿勢でいると腰が痛くなる」
・「運動不足のせいか、肩こりがひどい」
このような状態が続くと、痛みが慢性化しやすくなります。
なぜ痛みが続くのか? ~最新の研究から~
近年の研究で、慢性的な痛みのある人の脳は、痛みを感じる領域が通常とは違う動きをしている ことが分かっています。
例えば、2023年のある研究では、慢性的な痛みを持つ患者の脳をMRIで観察すると、以下のような特徴がありました。
✔ 「扁桃体(へんとうたい)」が活性化(不安や恐怖を感じやすい)
✔ 「視床(ししょう)」の働きが過剰(痛みの信号が強く伝わる)
つまり、「痛みが強く、不安も感じやすい」状態になってしまうのです。
また、「痛みを考えるだけで、実際に痛みが悪化する」 ことも確認されています。
「この痛み、治らなかったらどうしよう……」と考えると、本当に痛みが強くなるのです。
痛覚変調性疼痛の対策
では、どうすれば痛覚変調性疼痛を改善できるのでしょうか?
① 適度な運動をする
「痛いから動かさないほうがいい」と思うかもしれませんが、実は逆です。
適度な運動は、脳の痛みをリセットする働きがあります。
・軽いストレッチをする
・ウォーキングなど、ゆったりした運動をする
特に、ゆっくりとした動きの体操や、深い呼吸を伴う運動(ヨガやピラティスなど) は効果的です。
② ストレスをコントロールする
ストレスが強いと、痛みを感じやすくなります。
・趣味の時間をつくる
・深呼吸や瞑想を取り入れる
・リラックスできる時間を増やす
「まあ、大丈夫」と気楽に構えるだけでも、脳の警戒モードが和らぎます。
③ 睡眠と食事を整える
睡眠不足や偏った食事も、痛みを感じやすくする原因になります。
・質の良い睡眠をとる(寝る前のスマホを控える)
・バランスの良い食事をとる(特に、ビタミンB群やマグネシウムを含む食材が◎)
生活習慣を整えることで、脳の誤作動を防ぐことができます。
まとめ
痛覚変調性疼痛とは、「体の傷」ではなく「脳の誤作動」による痛みです。
しかし、脳の誤作動は、適切な方法でリセットできます。
✔ 適度な運動
✔ ストレス管理
✔ 生活リズムの改善
この3つを意識することで、痛みは少しずつ変わっていきます。
「もうこの痛みとは一生付き合うしかない……」と諦める前に、まずは小さなことから試してみませんか?
あなたの体は、きっと回復する力を持っています!